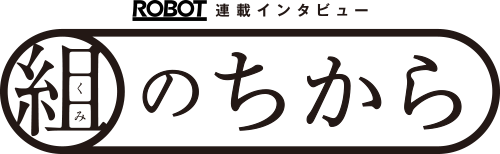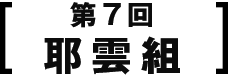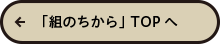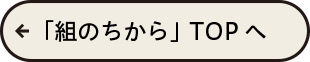多重なキャリア。そして長編デビュー作『百瀬、こっちを向いて。』

耶雲のものづくりの姿勢を理解する上で、押さえなくてはいけないのはそのキャリア。ROBOTに入社して、CMプランナーを経てのCMディレクターという職種で10数年。その中で前述のとおり、本人が「何でもやりたいし、何でもできる」と言ってきたことや、周りが耶雲の個性と才能を見抜いていたこともあって、さまざまな仕事がめぐってくることに。
耶雲:CMは本当に何も知らない世界だったので、就職した当初はとまどいがありましたね。学生時代にさかのぼれば自主映画やプロのピンク映画の現場をちょっと手伝ったこともありましたが、あまりお金のない現場だったので、周りは“役者の芝居を撮ってナンボや!”っていう考えだったりして。
でもCMの世界はそれなりにお金があって、いかにフレームの中の世界を作り込むか....っていうと、意識高いクリエイターみたいで照れるんですが(笑)、動くグラフィックみたいなところがあります。いかに見ている人をその気にさせるエッセンスを入れられるか。役者も大事な要素だけれども、同じくらい音楽や、効果音や、照明や、美術や小道具が大事で。そこがCMの演出の醍醐味の一つだと思います。でも、それはどのジャンルにも言えることですよね。バラエティも同じで、どれだけ引っ掛かりがあるのか。映画はさらに尺が長いので、流れの中でいかにそれを入れていけるか、なのかなと。
大学時代に出会った映画も仕事をしていくうえでいつかは手掛けてみたいと思っていたジャンル。ただ、そこがゴールではない。
耶雲:初めてやらせていただいた深夜の連ドラ(2010年『日本人の知らない日本語』読売テレビ・日本テレビ系)のプロデューサーがROBOTの映画部にいて、女の子の映画を撮りたいということで声を掛けてくれたのが『百瀬、こっちを向いて。』だったんです。当時、男の子的な映画が日本映画でもROBOT内でも多くて、それこそたまたま女の子を題材にしていたということで、巡り巡って僕のところに来たのかもしれないですね。僕自身も男の子映画より女の子の青春映画が好きで、女性をナチュラルに撮る映画をいつかやりたいと思っていたので、ぜひ、という感じでしたね。
もちろん、あるべきところには、こだわりはある。

耶雲:映画に関しては、やれるなら何でもいいと思っていたわけではなくて。自分のやりたいことや、自分が持っている力を活かせる作品かどうかは見極めていました。短いスパンのものであれば、ある種プロフェッショナルに徹して仕事はできかもしれないけれど、映画は仕事として大きなもので、期間や尺も長いですからね。得意なものや惹かれるものでないと、初めて自分がやるものとして意味がないんじゃないかと思っていました。
*